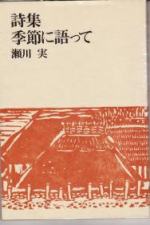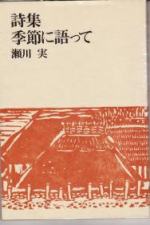|

詩集 季節に語って
瀬川 実
思潮社 昭和51年3月
生と死の大事を説くように季は巡る。
背をつらぬく苦痛の時間はあっても「詩」はなかなか生れてこなかった。
自分の中にひそむ和らぐことなくつづく熾烈さは、言葉とは永劫の
距離があるのである。 (あとがきより)
戻る
はっきりとぼくの内部(なか)で仏像は崩れ落ちてしまうのだろうか
自分にばかりとらわれた多弁の眠りに馴れて
とうとう坐ることひとつできなかった
仏像のまえで何度いやしい男の声をあげ
まくれた口唇を動かして悪態にはしったことか
微笑こそ仏の全体であったはずなのに
円相は剥げて虫だらけとなり今にも入寂してしまいそうなのだ
暁闇の冷たい風でふと目をあけると
そこに思惟され観ぜられて
若い肉体(からだ)は仏像をどんなにか重苦しいものと思ったことか
父母の坐ったところに仏像を斃して飛び出て行っても
どこまで行けるものか
此岸でのあらそいに立ちつくしてどこへもわたれないから
だれにもかかわらない薄明のもとでひとり
一瞬にも地にもどってしまいそうな仏像を
無言がささえている
家
生れてこの方住んだ葛屋根が
一日とかからず職人の手で剥ぎ下されて
すんだ水の流れる河原で燃え上った
どうしてか嫌悪のように傾いた家がこわされる最後にも
体のすみずみに語りかけてくると思わなかった
蔓草が草木にからむように手足のおよばないところに霊(いのち)がのびてくるのだ
背を寄りかけて行く末を案じた柱が倒れ煤煙を舞い上げると
ふるえながら時が逆流する
どんなにみかけが悪かろうとこのなかでこのなかの血が流れていて
これから先どこでくらそうとも遺跡のように体にうずまってゆく
家は住むためのいつわりをきっぱり捨てていい
こへも捨てられない凝縮こそ家でなくては
ぼくはながいながい空間を焼き続ける炎の消滅まで
炎とともにするのだ
季節
眠りからさめたとき蛙の声はやんで
鍵などかけたことのない戸のすきまから
昼とはすっかり変った風が流れ込んでくる
苗田の畔(くろ)にまだ残されて逆吊りされた鴉の屍骸が同類を悲しませていた
土用前にも干した青梅を三年ほどもたつ甕の汁で快く染めて
老母は楽しみを黙黙と子どもたちに届け伝えるだろう
砂のように砕かれて自らの目をおおってしまっても
顔だけは自然と季節の方に向いていよう
熟しても誰にも忘れられてしまった野の実のように
私はくりかえしくりかえし足もとに落ち重さなるだけで
もうどこへも跳べないだろうが
私の痩けた腹でも鴉が突きにきても
季節のように全部は食べられないだろう
あと三時間もすれば朝靄から「ででっぽう」が啼くにちがいない
|