|
初夢(ウロボロス) 秋葉宗一郎
夢に現れる場合、蛇はその形状から男性器の象徴とされるが、丸呑みという別の特性から、
実は女性器も暗示されている。自らの尻尾を啣え込んだウロボロスの蛇の吐息は、それゆえ
に世界のはじまりの隠喩となっている。瞬間の闇の反転とそれに続く急激な光の拡散、
すなわち、はじめられた世界において、夥しく孕ませられる析出が、希われた零度への回
帰に由来することは、骨を抜かれ失われた螺旋の悲しみから三和土への濡れた戸を叩きた
がる者と、抜かれた骨を包むことで他律から自律への電荷を負う者とで、繰り返される略
奪の主体が誤解されてきたことに通底する。さらに、満潮の汀に肥えるウロボロスの蛇は、
一匹ではなく、尻尾から丸飲みされた無数の蛇の集合体であるのだが、そのことは、蛇の
身体に沿ってうすい切れ目を走らせ、それが円に繋がった所でめくり取られるパリパリし
た油紙のような表皮が、この作業を繰り返すことで無限に近い程度得られることに示され
ている。(このパリパリした表皮には、独特の紋様が残されていて、そこに意味を重ね、あ
る種の予言を弄ぶ破廉恥な連中が跡を絶たないが、その蠱惑性は、たっぷりと湛えられた
光の海に流れる水脈(みお)のような黒い航跡の、その果てには決して辿り着くことができ
ないことに因っている。)

❑初夢(ウロボロス)
合評会用の作品としてもらったのは、タイトル通りの巳年が始まって間もなくのことだったと思う。
途中で、ぷっ。噴き出してしまい、にやにやしながら読み終えた。どうしたってこれは,詩、詩人、現代詩に関わっているこの世界の「隠喩」だ。
「骨を抜かれ…叩きたがる者」とは、いわゆる抒情詩(人)だろう。
「抜かれた骨を…負う者」つまりはいまどきの難しい現代詩で、例えばこんなふう、と秋葉さんは器用に書いてみせている。詩を書いている人たちが集まっている席などたしかに 「尻尾から丸飲みされた無数の蛇の集合体」そのもの。 「このパリパリした表皮には…」からにはまたまた笑ってしまう。
けれど、皮肉たっぷりのようでいて、秋葉さん自身も抜けられない世界の一人であることを確認している。そしてなおも辿リ続けるという、ひそやかな抱負が込められている気がする。
といったことを申し上げたが、相変わらず秋葉さんは何も言わずニコニコしていた。
我が身に引寄せすぎたか。さて??
|
|
|
黒猫ナナ たかとう匡子
噛む
のとはちがう
でも痛い
まじかに来ているのは知っていた
渓谷の地下に埋もれていた古代村落が発掘されたという記事
がとびこんできたけど知らんぷりしていた
黒猫ナナは伸び上がって二の腕に爪をたてる
村落は楡や柏の森におおわれていた
ひとびとは
半島を海から海へと横断していたよ
とつぜん話しかけてくる
黒猫ナナ
ざらり舌触り
毛並みのなかで光る金色の目の構成する光景が
開かれたり閉じられたり
何が言いたいの
そしてだれにむかって
解不能のバランス感覚
おまえとわたしの
長いしっぽ
のたりくたり
前後左右にうごかして
わずか数本の樹木がまばらに立つ窪地の奥
埋もれていたはずの
古代村落のあたりをしきりに舐めている
いたものがいなくなる
その距離
疼く
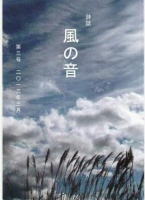
2013/03
❑黒猫ナナ
遺跡や遺骨発見のニュースは、あやふやな知識しか持たない私も心躍る。文明や人類といった大きなくくりを思うからだろうか。時に梳かされてなんだか明るい。
しかし数千年、数万年前でなく、今。「いたものがいなくなる」。
いつもいたひとは、発掘の仕事に携わっていたのか、遺跡に興味を持っていたのか、こんど一緒に行こうと話してしたのかもしれない。黒猫を撫でながら埋もれた村落について書かれた本をめくっていたひとだったのかもしれない。舐めている「古代村落のあたり」はソファの窪みだろうか。
もういないのに、つい呼びかける。物なら手にとろうとして、あら? その瞬間、思い知らされる。生身の時間に欠落の深みを覗こうとするなら素知らぬふりで近づくしかないだろう。
おまえとわたしの/ 長いしっぽ/ のたりくたり
この「のたりくたり」にも無防備を装っている響きがあって、かなしい。
|
|
|
家 橋本千秋
犬がいた頃、四時になると家の中を覗いて待
っていた。散歩のコースは決まっていて、公
園を横切り住宅街を抜け、雑木林の中を歩い
て帰ってくる。小一時間の散歩だが、いつの
頃からか時々、帰って来ても家に入らず、家
の前を通り過ぎる。名を呼んでも振り返らな
い。散歩が足りないとか、どこか行きたい所
があるとか、そんな風でもなく家の周りを一
周すると、おとなしく家に入る。
夕方、ひとり帰るいつもの道。家を見ながら、
家の前を通り過ぎる。家の周りを一周して入
る。

2012/05
❑家
まだ明るかったり、薄暗い時期だったり、四季折々の夕暮れの中を犬と散歩する姿はどこでも見かけるから、すんなり情景が浮かぶ。何も説明は要らない。すっと読んで、すっと通り過ぎる。…かと言えば、そうはいかない。例えば、見慣れた川面にさざ波を見つけてしげしげ覗き込んでいるといったふう。かすかな風や光、立ち位置や流れの底を思うともなく思いながら。
家を見ながら、家の前を通り過ぎる。家の周りを一周して入る。
犬と同じことをしている自分に気づいた微苦笑や、この頃の出来事と結び付けて何かの不安がそうさせるなどとわかった気はしても、それだけで片付けられずまた読み返す。
家も、無くなると「私」の根拠(のようなもの)が揺らぐ。そういうものを無意識のうちに確かめているのだろうか。「いつの頃からか」で老犬を想像してしまう。呼ばれても振り返らずにながめていた犬も、老いた人が時折りみせる放心したような安堵のようなまなざしだった気がする。
いかにも詩!らしい言葉はいっさい使わず、けれど、それしかない言葉で書く。見習いたいと思う。 |
|
|
あんぱん 豊田和司
げんばくがおちたつぎのひ
あてもなくまちをあるきつづけた
きがつくといつのまにか
しらないおんなのこがついてくる
あっちへいけ!
おいはらっても
おいはらっても
おんなのこはついてくる
ていぼうにこしをおろして
ひとつだけもっていたあんぱんをたべた
おんなのこもとなりにすわって
あしをぶらぶらさせていた
くすのきのねもとで
よるはのじゅくした
おんなのこもすこしはなれて
ごろりとよこになった
よくあさめがさめると
おんなのこはつめたくなっていて
なにごともなかったかのように
ぼくはまたあるきはじめた…
いまでもときどきおんなのこは
ゆめのなかであしをぶらぶらさせていて
あんぱんをわけてやるのは
いまこのときだとおもって…
いつも
なきながら
めがさめる
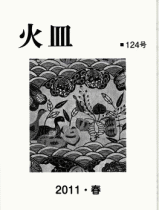
2011/春
❑あんぱん
おんなのこの、泣き笑いのような、途方にくれたような、どこか安心したような表情がみえる。
彼女は、石原吉郎でいえば、もう尻のあたりがすきとおっているのだ。だから追い払ってもついてくる。あんぱんより「ぼく」の生命、滞りない血液の温もりにひきずられて。
あしをぶらぶらさせていた
それだけで、どのような姿恰好なのか一切の描写はない。ないのに、みえる。原爆図でみたような姿をぼんやり浮かべているが、おどろおどろした印象は残らない。あの時。あの時。あの時のことを「いつも なきながら めがさめる」ほど悔んでいるだけでお決まりの告発はない。ないのに、聞こえてくる。
深い悲しみはよほど雄弁だと思う。
豊田さんにとって「げんばくがおちたつぎのひ」でなければならないが、読む側にはたとえば震災の、津波の、事故の、空襲の、失敗の、それぞれの個人的体験の「つぎのひ」に重ねて共感しても許される気がする。 |
|